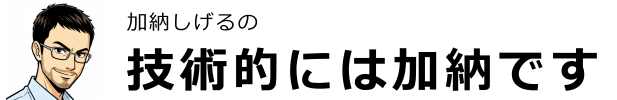「技術的には可能です」が持つ不思議なニュアンス
システム開発の現場で耳にタコができるほど聞くフレーズ――それが「技術的には可能です」だ。
一見するとポジティブで希望を与える言葉に聞こえるが、その裏には複雑な事情が隠れている。発言したエンジニアの心の声は「やりたくない」「コストが爆発する」「仕様が地獄」…など実にバリエーション豊かだ。
この記事では、この言葉に潜む本音を暴き、なぜ「可能」と言いつつ顔が死んでいるのかを解説する。そして読者が次に「技術的には可能」と言う時に、自分の立場を正しく伝えられるようになることを目指す。
結論:可能は可能、だが現実的かは別問題
結論から言えば、「技術的には可能です」はほとんどの場合、「できるけど、現実的にやりたくない」の婉曲表現である。
エンジニアがわざわざ「技術的には」と前置きするのは、単なるYes/Noで答えられない背景があるからだ。コスト、納期、運用、リスク…そのどれかがネックになっている。
つまり、依頼者が「じゃあすぐにやってよ」と安易に考えるのは危険だ。この言葉を聞いたら「なぜ実現が難しいのか」を掘り下げる必要がある。
「技術的には可能です」に隠された真意
1. コスト爆発型
「できます。ただし予算は3倍、納期は半年延びます」――このケースが一番多い。
技術的には問題なくても、リソースの消費が大きすぎる場合だ。例えば以下のような状況がある。
- 既存システムをゼロから書き換える必要がある
- 利用ライブラリが対応していないため自作が必要
- サーバ増強やクラウド費用が膨れ上がる
この場合の本音は「可能だけど、あなたの財布は死ぬ」だ。
2. 運用地獄型
「できます。ただし運用担当者は泣きます」――リリース後に現場の負担が増えるパターンだ。
例えば、毎回のリリースに手作業が必要になる、異常系の切り戻しが地獄、ログ解析がブラックボックス化するなど。
エンジニアはこの未来を予感しているため、あえて「技術的には」と枕詞をつけるのだ。
3. リスク未踏型
「できます。ただし動くかはやってみないと分かりません」――要するに実験段階で、本番で安定稼働する保証がないケースだ。
特に新技術を導入する時によく使われる。「理論上は可能だが、誰もやったことがない」「Stack Overflowに事例がない」などが典型例。
この場合の本音は「俺も怖い」である。
4. 仕様カオス型
「できます。ただし仕様がブレブレです」――要件が固まっていないのに実装を迫られるケースだ。
仕様が動くたびにコードも動く。結果として工数が青天井になる。
このときの本音は「可能だけど無限にリファクタする羽目になる」だ。
データと事例:プロジェクト失敗要因
IPA(情報処理推進機構)の「ソフトウェア開発データ白書」でも、失敗プロジェクトの要因トップは「要件の不明確さ」「スケジュール遅延」「コスト超過」であると報告されている。
つまり「技術的には可能です」の裏側にある事情と、統計的な失敗要因はほぼ一致している。表面上は「できる」と言いながら、現場が冷や汗をかくのはこのためだ。
どう向き合うべきか
「技術的には可能です」と言われたら、以下の観点で追加質問するのが効果的だ。
- コストはどれくらい増えるのか?
- 納期にどんな影響があるのか?
- 運用や保守に追加負担はないか?
- 想定外のリスクは何か?
この問いを投げかけることで、単なるYes/Noでは見えない真実が明らかになる。
エンジニア側も「できるかできないか」でなく「やるべきかどうか」で話ができるようになる。
まとめ:魔法の言葉にだまされない
「技術的には可能です」は便利なフレーズだ。しかし、それを鵜呑みにするとプロジェクトは簡単に迷走する。
大切なのは、その言葉の裏にある現実を正しく把握することだ。
次にこのフレーズを耳にしたら、ぜひ追加質問で深掘りしてほしい。そうすれば、依頼者とエンジニア双方が納得できる選択肢を見つけられるはずだ。