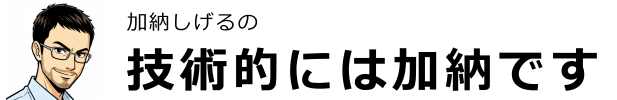「インフラがわからない情シスは詰む」──その言葉の意味とは?
社内システムが落ちた。誰もメールを送れない。プリンタも動かない。
上司の第一声はこうだ。「情シス、なんとかして!」。
しかし、あなたがアプリ担当であっても、インフラの仕組みがわからなければ、何もできない。
どこで障害が起きているのか、ネットワークかサーバか、判断すらつかない。
その結果、ベンダーに丸投げし、時間とコストを浪費する。──これが現場のリアルだ。
この記事では、「情シスにインフラ知識が必要な理由」を、現場感たっぷりに解説する。
そして、あなたが今後どんなスキルを身につければ、詰まない情シスになれるのかを具体的に紹介しよう。
情シスが生き残るための最重要スキルは「インフラ理解」だ
結論から言おう。
情シスが今後も社内で信頼され、価値を発揮し続けるためには、インフラの知識が必須だ。
なぜなら、クラウドの時代になっても、アプリもデータも、すべてインフラの上で動いているからだ。
インフラとは、サーバ・ネットワーク・ストレージ・セキュリティなどの基盤のこと。
つまり、建物でいえば「基礎」。
アプリがいくら立派でも、基礎が弱ければすぐに崩れる。
そして、現場ではこの「基礎」をわかっている人が圧倒的に少ない。
多くの情シス担当者が、「サーバはベンダー任せ」「ネットワークは別部署」と分業の壁に閉じこもってしまう。
だが、クラウド環境ではそれが通用しない。
AWSでもAzureでも、ネットワーク設計・セキュリティ設定・権限管理は、すべて情シスの責任範囲になる。
つまり、「情シス=インフラの番人」。
この自覚を持たないと、いずれAIにも置き換えられてしまうだろう。
現場で起きている「詰む」瞬間たち
VPNがつながらない、でも原因がわからない
リモートワーク中の社員から「VPNがつながらない!」という問い合わせ。
よくある話だ。
ここで「ベンダーに聞きます」と言ってしまう情シスは、残念ながら“詰み”の始まりだ。
VPNのトラブルは、ネットワーク・認証・クライアント設定・証明書など、どこにでも原因が潜む。
Ping、tracert、nslookupといった基本コマンドで状況を切り分けられる知識があれば、一次対応ができる。
だが、これができないと、対応は何時間も遅れ、現場からの信頼を失う。
ping 10.0.0.1 tracert hoge.com nslookup vpn.example.co.jp
この3行を打てるかどうかで、情シスとしての“格”が変わる。
クラウドの請求額が爆増、でも理由が説明できない
「AWSの請求が先月の3倍なんですが?」
CFOの怒りの声。情シスに冷たい視線が刺さる。
原因はEC2インスタンスの無駄な常時起動か、S3への大量バックアップか。
どちらにしても、リソース構成を理解していないと説明すらできない。
インフラの知識は、単なる技術スキルではなく、会社のコストを守るためのビジネススキルでもある。
セキュリティ対応が後手に回る
ゼロデイ脆弱性が発覚。
「うちの環境は影響ありますか?」と聞かれても、サーバ構成を把握していなければ何も言えない。
OSのバージョン、パッチ適用状況、公開ポート――
これらを管理できるのは、インフラを理解している人だけだ。
セキュリティ担当者は魔法使いではない。
「構成情報がわからない情シス」=「火事場で地図を持っていない消防隊」だ。
インフラ知識が情シスを強くする理由
1. トラブル対応力が爆上がりする
障害発生時、インフラの知識がある人は原因を素早く特定できる。
ネットワーク経路、ログ、CPU負荷、ディスクIOなど、見るべきポイントを瞬時に判断できる。
結果、復旧が早くなり、「頼れる人」として社内で評価が上がる。
2. ベンダーとの交渉が有利になる
インフラを理解していれば、業者が出してきた見積りが妥当かを判断できる。
「この構成は冗長すぎでは?」「SLAが不要に高くない?」と指摘できるのは、知識を持つ人だけだ。
つまり、技術の知識はコスト削減の武器にもなる。
3. DX推進に不可欠な存在になれる
DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるうえで、クラウド・API・ゼロトラストなどのインフラ知識は欠かせない。
社内のアプリ刷新を進めるにも、基盤を理解している情シスがいなければ、プロジェクトは迷走する。
最終的に、インフラを理解している情シス=会社のIT戦略を動かせる人になる。
インフラ知識を身につけるためのステップ
Step1:Linuxとネットワークの基礎を学ぶ
まずは、サーバを触ってコマンド操作に慣れる。
おすすめは、自宅PCに仮想環境を作り、CentOSやUbuntuを入れて遊ぶこと。
「ping」「top」「netstat」などの基本コマンドを叩きまくれ。
Step2:仮想化とクラウドを理解する
VMware、Hyper-Vなどの仮想化から入り、次にAWSやAzureの無料枠で環境を構築してみる。
「サーバを立てる」→「ネットワークを設定する」→「セキュリティを考える」
この流れを手を動かして覚えるのが最速だ。
Step3:セキュリティと自動化を学ぶ
最後はセキュリティと運用自動化。
ファイアウォール設定、ログ監視、スクリプト化(PowerShellやPython)などを理解すれば、立派な情シスインフラ担当だ。
| 分野 | おすすめ技術・ツール |
|---|---|
| OS | Linux, Windows Server |
| ネットワーク | TCP/IP, DNS, VLAN, VPN |
| クラウド | AWS, Azure, GCP |
| 仮想化 | VMware, Hyper-V |
| 自動化 | Ansible, Terraform, PowerShell |
これらを少しずつ触りながら、「動かして理解する」ことが重要だ。
情シスの未来は、インフラ理解が決める
クラウドが普及し、AIが台頭しても、システムの“基盤”を理解している人の価値は変わらない。
むしろ、基盤をわかっている人ほど、新しい技術を正しく選び、使いこなせる。
インフラを理解する情シスは、社内の「守り」と「攻め」の両方を担える存在だ。
障害対応という守りを固めつつ、DX推進という攻めにも関われる。
これほど面白いポジションはない。
もしあなたが「今の仕事が物足りない」と感じているなら、
ぜひインフラの世界に一歩踏み出してみてほしい。
最初は地味に見えるが、理解が深まるほど、会社のITの全体像が見えてくる。
そのとき、あなたはもう“詰まない情シス”だ。