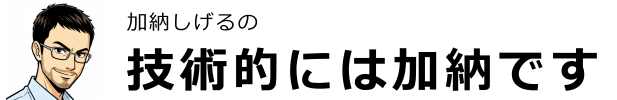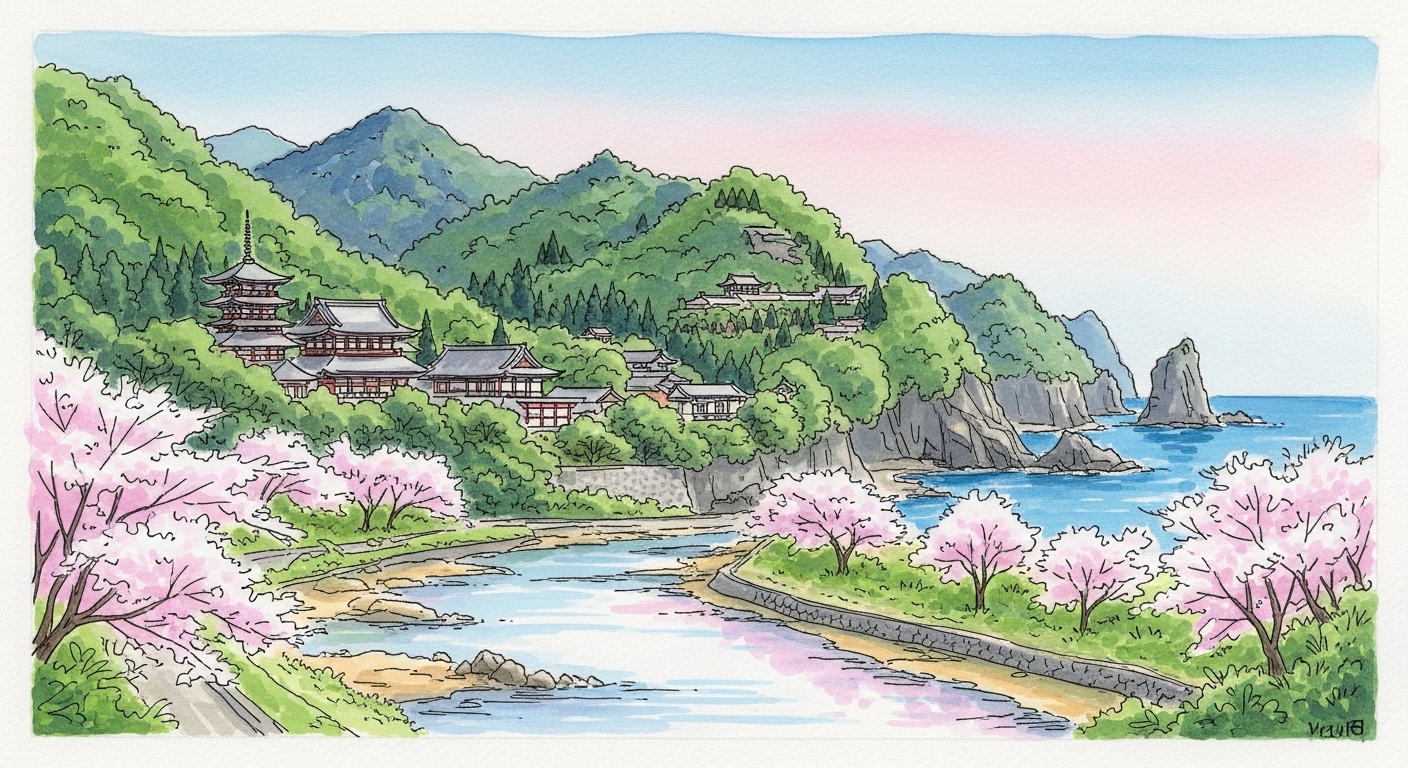エンジニアを目指すときに気になる「現場」
「エンジニアになりたいけど、システム開発の現場ってどんな雰囲気なんだろう?」──そんな疑問を持つ人は多い。特に日本では「Sier」という独特の業態が存在し、その中で働くことがエンジニアのキャリアの入口になるケースも少なくない。この記事では、Sierのシステム開発現場がどのような場所なのかを、リアルな視点で解説する。読めば「自分がそこでやっていけそうか」のイメージがつかめるはずだ。
結論:Sierの現場は「人とプロセス」で動く世界
Sierのシステム開発現場は、最新のテクノロジーを駆使するというより、人の連携とプロセス管理が中心の場所だ。大規模案件では数十~数百人規模のチームが関わり、要件定義からテスト、運用まで「ウォーターフォール型」と呼ばれる工程に沿って進む。現場は、調整・会議・資料作成・テストといった「地味だが重要な仕事」にあふれている。つまり、「最初からゴリゴリ開発して最新技術を使いたい!」という人にはギャップがあるかもしれない。
Sier現場の基本構造
ピラミッド型の多層構造
Sierのプロジェクトはピラミッド構造で動く。元請け(大手Sier)が顧客と直接やりとりし、その下に中堅・中小Sier、さらに外注や派遣エンジニアが入る。いわゆる「多重下請け構造」だ。この構造の中で、自分がどのポジションにいるかで仕事内容が大きく変わる。
工程ごとの役割
| 工程 | 主な作業内容 | 現場での雰囲気 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 顧客との打合せ、仕様の言語化 | 会議だらけ。PowerPointが武器 |
| 設計 | 詳細設計書の作成 | ExcelとWordに埋もれる毎日 |
| 実装 | 設計書に基づきコーディング | 比較的静かだが納期前は修羅場 |
| テスト | 仕様通り動くか確認 | 単純作業が多く、新人の登竜門 |
| 運用・保守 | リリース後の障害対応 | 電話が鳴りっぱなしで胃が痛くなる |
データから見るSierの実態
経済産業省のIT人材白書によれば、国内SIビジネスの約7割は大規模な受託開発に費やされている。案件規模は億単位になることも多く、関わる人員の数も桁違いだ。「個人のスキル」より「プロジェクトマネジメント力」が重視される傾向が強いのがSier現場の特徴といえる。
現場のリアルな体験談
新人時代はテスト要員からスタート
多くの新人エンジニアは「テスト工程」からキャリアを始める。正直に言えば、単純作業が多く「自分はエンジニアなのか?」と疑問に思うこともある。しかし、ここでシステム全体の流れを理解できるため、後々の設計や実装に役立つ。地味だが意味のある下積みだ。
資料作成のスキルが身につく
Sier現場では、コードを書く時間より資料を作る時間の方が長い場合がある。仕様書、設計書、議事録、進捗報告──資料の種類は尽きない。だが、この経験を通じて「相手にわかりやすく伝える力」が磨かれるのは間違いない。エンジニアでありながら、プレゼン力や文書力が鍛えられるのはSierならではだ。
コミュニケーションが最重要
Sierの現場はチーム作業が基本だ。顧客との調整、上司への報告、下流工程への依頼──毎日がコミュニケーションの連続だ。黙々とコードを書くだけではなく、人とのやりとりをいかにスムーズにこなすかが、評価やキャリアに直結する。
メリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
まとめ:Sier現場は「技術」より「人と仕組み」を学ぶ場
Sierのシステム開発現場は、最新技術を駆使する華やかな場所ではない。むしろ、人とプロセスをコントロールするスキルを鍛える場だ。ここで得られるのは、調整力・文書力・マネジメント力といった「技術以外の武器」であり、それはキャリアを長期的に支える強力な財産となる。
これからエンジニアを目指す人は、自分が「技術を突き詰めたいタイプ」なのか、「人と仕組みを動かしたいタイプ」なのかを意識してキャリアを選ぶとよい。もし後者に魅力を感じるなら、Sierの現場は確実に成長の場になるだろう。