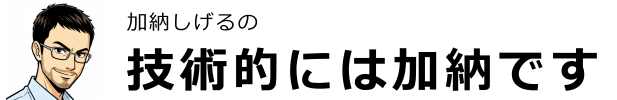クラウドの稼働率99.9%とは?1年でどれだけ止まるのかを数字で解説
クラウドは「ほぼ止まらない」って本当?
「クラウドの稼働率は99.9%です」と聞くと、ほとんど止まらないように感じる。
しかし、実際に数字にしてみると「99.9%」は意外と止まっている。
AWSやAzureのSLA(サービス品質保証)にも書かれているが、
「99.9%稼働」というのは「1年のうち、一定時間は止まっても許容される」という意味だ。
つまり、「99.9%稼働」=「100%稼働ではない」。
この記事では、
クラウドの稼働率の意味、具体的な停止時間、そしてそれを支える指標(MTBF・MTTRなど)について、
数字を交えて分かりやすく解説していく。
きっとこの記事を読み終える頃には、あなたの頭の中に「99.9%=魔法ではない」という現実が残るだろう。
—
「99.9%稼働」の真実:実は年間8時間以上止まっていい
まず結論から言おう。
1年=365日=8,760時間。
「稼働率99.9%」とは、そのうち約8.76時間の停止が許されるという意味だ。
以下の表を見てほしい。
| 稼働率 | 年間停止時間 | 月間停止時間 |
|---|---|---|
| 99% | 約87.6時間(約3.6日) | 約43分 |
| 99.9% | 約8.76時間 | 約4.4分 |
| 99.99% | 約52.6分 | 約26秒 |
| 99.999% | 約5.26分 | 約2.6秒 |
つまり、99.9%は「ほぼ止まらない」ではなく、「年に半日くらいは止まっても文句は言えない」ということだ。
ファイブナイン(99.999%)まで行ってやっと「年に5分しか止まらない」世界に到達する。
—
数字で見る「稼働率」「MTBF」「MTTR」
稼働率の計算式
クラウドの可用性を表す「稼働率」は、以下の式で表される。
稼働率 = 稼働時間 ÷ (稼働時間 + 停止時間) × 100
例として、もし1年のうち丸2日止まった場合:
稼働率 = (8760 - 48) ÷ 8760 × 100
= 8712 ÷ 8760 × 100
≒ 99.45%
つまり、「たった2日止まっただけ」で稼働率は99.45%まで下がる。
クラウドサービスがいかに高い稼働率を維持しているかが分かるだろう。
—
MTBFとMTTRとは
「可用性」は稼働率だけでは語れない。
そこで登場するのが、次の2つの指標だ。
- MTBF(Mean Time Between Failures):平均故障間隔。どのくらいの間隔で故障が起きるか。
- MTTR(Mean Time To Repair):平均修復時間。故障してから復旧するまでの平均時間。
これらを使うと、稼働率は次のようにも表現できる。
稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)
たとえば、
* 故障が平均1000時間ごとに発生(MTBF=1000)
* 修復に1時間かかる(MTTR=1)
なら、稼働率は
1000 ÷ (1000 + 1) = 99.9%
…そう、これがまさに「スリーナイン」の世界だ。
ちょっとした設定ミスやネットワーク障害があっても、1時間以内に直せば99.9%を維持できる計算になる。
—
現実のクラウドはどれくらいの稼働率なのか
主要クラウドベンダーのSLA(サービス品質保証)を見ると、実際の稼働率がわかる。
| クラウドサービス | SLA(稼働率) |
|---|---|
| AWS EC2 | 99.99% |
| Microsoft Azure VM | 99.95% |
| Google Cloud Compute Engine | 99.99% |
いずれも「フォーナイン」クラス。
しかし、注意したいのはSLAは「保証値」であって、実績値ではないという点だ。
実際に障害が起きた場合、ユーザーは返金などの補償を受けられるが、止まってしまった事実は変わらない。
—
障害はどこでも起きる
2023年には、AWS東京リージョンで大規模なネットワーク障害が発生した。
また、Azureでも一部の認証系サービスが数時間停止したことがある。
どちらも「フォーナイン」をうたうクラウドだ。
どんなに設計が優れていても、
人間が設定し、人間が運用している以上、障害ゼロはありえない。
クラウドは「止まらない魔法の箱」ではなく、 “止まっても早く直るように設計されたシステム”なのだ。
—
稼働率を上げるための設計思想
可用性を高めるためには、単に「信頼できるクラウドを選ぶ」だけでは不十分だ。
アプリケーション側にも工夫が必要になる。
1. 冗長化(Redundancy)
サーバーを複数台構成にする、AZ(アベイラビリティゾーン)をまたぐ配置をすることで、
1台(あるいは1拠点)が落ちてもサービスが継続できる。
2. フェイルオーバー
障害発生時に別系統に自動的に切り替える仕組み。
DNS切り替えやロードバランサで実装する。
3. モニタリングと自動修復
異常を早期検知し、自動で再起動や切り替えを行う。
この「MTTRの短縮」が結果的に可用性を押し上げる。
4. キャパシティプランニング
負荷ピーク時にサーバーが落ちないよう、リソースの余裕を見積もる。
スケーリング戦略の設計もここに含まれる。
—
「99.999%を目指す」と言われたらどうする?
上司が「ファイブナインを目指したい」と言い出したら、
まず深呼吸してから電卓を取り出そう。
99.999%は「年に5分しか止まれない」水準だ。
冗長構成、二重回線、データレプリケーション、24時間体制の監視――
つまり、金がかかる。
本当にそこまでの可用性が必要なのか?
「5分止まっても困らない」なら、99.9%でも十分だ。
「5秒も止まれない」金融取引系なら、専用線+オンプレ構成の方が現実的な場合もある。
可用性は「どれだけ止まらないか」ではなく、 「止まってもビジネス的に許容できるか」で決めるのが正解だ。
—
まとめ:数字の裏側を理解して、現実的な設計を
最後にこの記事のポイントを整理しよう。
- 「99.9%稼働」は年間約8.76時間の停止を意味する
- 2日止まると稼働率は約99.45%
- 可用性は「MTBF」「MTTR」のバランスで決まる
- SLAは「保証値」であり「実績」ではない
- 可用性向上には冗長化・フェイルオーバー・監視が不可欠
- ファイブナインはコストとトレードオフ。目的に応じた水準設定が重要
「クラウドだから止まらない」は幻想だ。
しかし、適切な設計と監視で「止まってもすぐ復旧できる」状態にすることはできる。
もしあなたがインフラエンジニアとして
「もっと可用性を上げろ」と言われたら、ぜひこう答えてほしい。
「それ、何分まで止まっていいサービスですか?」
数字の裏側を理解することが、
信頼されるエンジニアへの第一歩である。