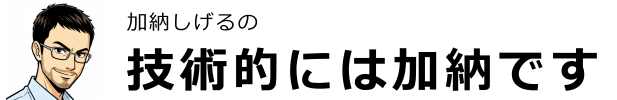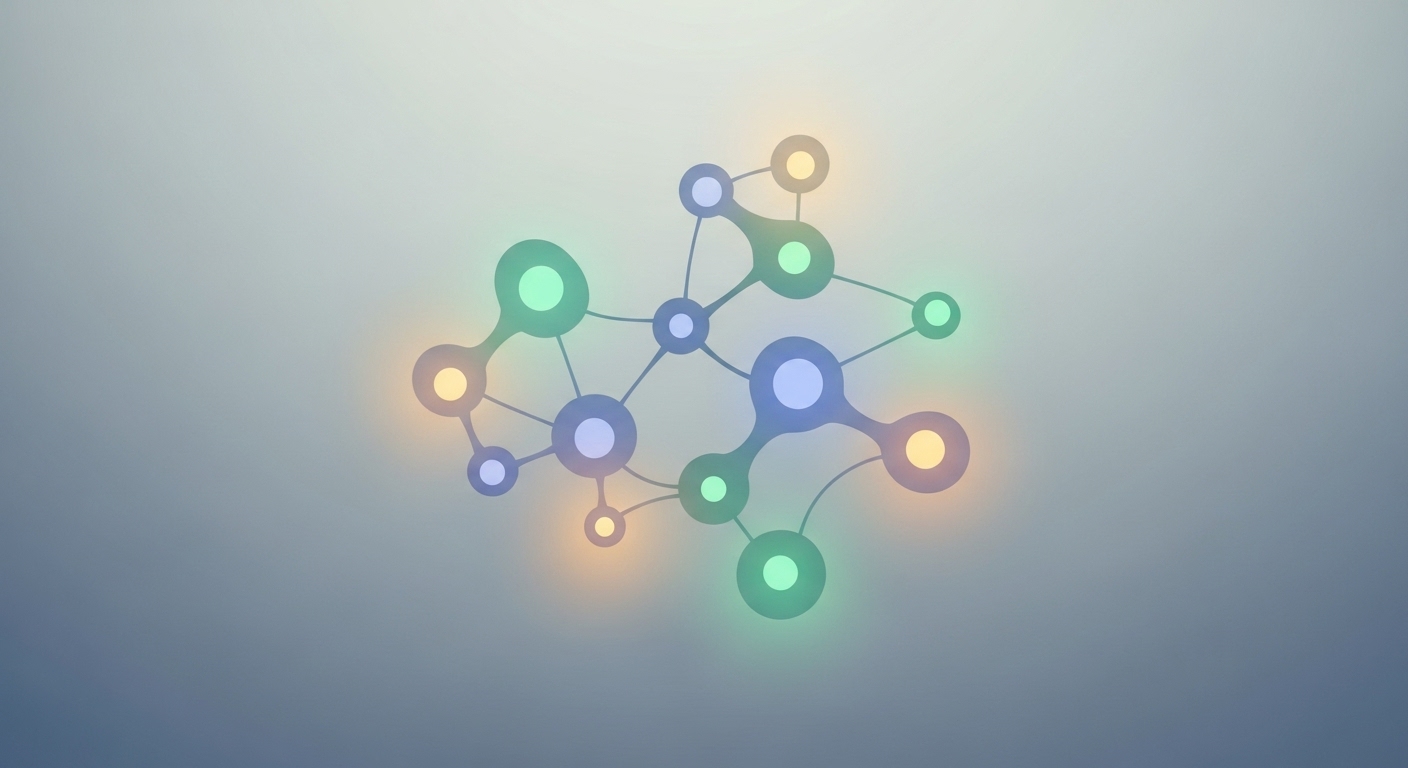文章力でエンジニアの評価が変わる時代へ
「仕様書の日本語がなんだか幼く見える」「レビューで“表現を統一してほしい”と指摘された」──そんな経験はないだろうか。
技術力だけで勝負していた時代は終わり、“伝える力”も評価対象となる今、エンジニアに求められるのは、論理的で一貫した文書表現だ。
本記事では、技術文書における「サ変動詞」──つまり「名詞+する」の表現を使いこなすことで、文書の質をワンランク上げる方法を紹介する。
読むだけで、あなたの設計書・仕様書が“できる人の文章”に変わる。その秘密を今すぐ見ていこう。
技術文書では「サ変動詞」を使うのが基本
まずは結論から言おう。
技術文書では、動作を「名詞+する」で表すのが基本だ。
例えば次のような違いを見てほしい。
| 一般的な表現 | 技術文書で適切な表現 |
|---|---|
| ボタンを押す | ボタンを押下する |
| 設定を変える | 設定を変更する |
| ログを出す | ログを出力する |
| ユーザーを追加する | ユーザーを登録する |
| 通信を止める | 通信を停止する |
「なんだ、言い換えただけじゃないか」と思うかもしれない。だが、この“言い換え”こそが、文章の客観性と再現性を高める鍵なのだ。
なぜサ変動詞が好まれるのか?
1. 客観的であいまいさが少ない
たとえば「ボタンを押す」と書かれていると、どのボタンを、どのように押すのか曖昧になりやすい。
一方で「ボタンを押下する」と書けば、システム用語として明確に「押下イベントを発生させる操作」と認識される。
つまり、プログラムや設計の世界で通じる“正確な言葉”になる。
2. 名詞化することで文の構造が安定する
サ変動詞を使うと、文の主語・目的語を明確に構造化できる。
たとえば次の例を見てみよう。
【悪い例】 ユーザーがボタンを押したときに、データをサーバーに送る。
【良い例】 ユーザーによるボタンの押下時に、データをサーバーへ送信する。
後者は名詞を中心に構成されており、情報の整理と検索が容易になる。
つまり、読んだ瞬間に「押下時」「送信」というイベントや処理の関係が頭に入るのだ。
3. チーム全体の表現が統一される
「押す」「クリックする」「押下する」「タップする」など、似た表現が混ざるとレビューで混乱を招く。
サ変動詞を使えば、表現の標準化がしやすく、設計書の一貫性を保てる。
大規模プロジェクトほど、こうした統一ルールが品質を左右する。
どんな言葉をサ変動詞にすべきか
サ変動詞の世界は深い。だが基本ルールを押さえれば怖くない。
以下に代表的なカテゴリと例を挙げる。
操作・動作系
- クリックする → 押下する
- 変える → 変更する
- 消す → 削除する
- 作る → 作成する/生成する
- 出す → 出力する/送信する
- 止める → 停止する
状態・プロセス系
- 始める → 開始する
- 終わる → 終了する
- 動く → 動作する
- つながる → 接続する
- 入れる → 登録する/設定する
エンジニア界でよく出る“迷いやすい”表現
| NG | OK | 備考 |
|---|---|---|
| 画面を出す | 画面を表示する | “出す”は曖昧 |
| 値を変える | 値を更新する/変更する | 「更新」は既存値を上書きする意味で使う |
| ログを残す | ログを出力する/記録する | 「残す」は非技術的な表現 |
| 接続を切る | 接続を切断する | サ変化で名詞化 |
| ユーザーを作る | ユーザーを登録する/追加する | 「作る」は物理的で曖昧 |
やりすぎ注意!「サ変病」にご用心
とはいえ、「すべてをサ変にすればいい」というわけではない。
たとえば「休憩する」を「休憩を実施する」と書くと、もはや軍事報告書のようだ。
可読性と自然さのバランスが重要である。
また、設計書では「登録する」でよくても、ユーザー向けのマニュアルでは「追加する」の方が親切だ。
要は、読者が誰かを意識して使い分けることが肝心だ。
実際の文書での応用例
以下は、仕様書や設計書でよくある文の書き換え例だ。
【修正前】 ユーザーが設定を変えたときに、システムは新しい値を保存する。
【修正後】 ユーザーによる設定の変更時に、システムは新しい値を保存する。
「変えた」→「変更した」とすることで、文書全体が引き締まり、技術文書としてのトーンが統一される。
特に仕様書のレビューやドキュメント自動生成ツールを使う現場では、この違いが成果物の品質を左右する。
まとめ:サ変動詞を味方にすれば“伝わる文書”になる
- 技術文書では「名詞+する」で表現するのが基本
- 客観性・統一性・検索性が向上する
- すべてをサ変にせず、読者に合わせて使い分ける
技術力が高くても、文書で伝わらなければ意味がない。
サ変動詞を使いこなせば、設計書・仕様書・議事録まですべてが洗練される。
今日からあなたも、「押す」ではなく「押下する」エンジニアになろう。